「やっぱり・・・書くのやめようかな」
珍しくとーこが弱気なことを言ったので、俺は驚いて、向かい側で鉛筆を置いてしまったとーこを見た。
とーこん家のリビング。テーブルに2人分の原稿用紙。
とーこのばあちゃんが、煮物を作る匂いが立ち込めてた。
懐かしい匂い。
「・・・なんで?」
俺の問いかけに、とーこは寂しそうに俯いて「だって・・・」と暗い声を出した。
「・・・だってさ・・・発表の時笑われそうなんだもん。」
「んなの、気にすんなんよ」
「でも・・・」
・・・そっか、有菜のことで、田中たちとうまくいってないから・・・。
とーこの手元を覗き込めば、書き込まれていた文字が消されていた。
「将来の夢、だろ。笑わないよ、誰も。」
「う・・・ん・・・」
「翻訳家、だろ?"いろんな国の言葉を勉強して、いろんな国の絵本を紹介したい"」
それまで漠然としていたイメージを、とーこは1/2成人式の文集に書くためにちゃんと言葉にしてまとめた。
とーこの将来の夢の、どこが"笑われる"ようなことだ?
「笑われるなんて、ひとつもおかしなとこないのに?」
俺の言葉に、とーこはそっと顔をあげて弱々しく笑う。
「直人、あたしが言ったのちゃんと覚えてるんだ?」
「あたりまえじゃん。とーこが持ってる本、あれ全部訳すっていう約束だって覚えてるよ?」
「・・・そっか」
とーこは少し笑って、じっと原稿用紙を見つめた。
「何か言われたのか?」
俺の質問に、とーこは頷くことも首を振ることもせず、ただ「なんでもないよ」と答えた。
嘘なんだとわかる。
なんでもないわけない。
学年全体での発表会は明日。
今日、とーこのクラスでも発表練習があったはずで。
その時に何か言われたんだろう。
俺は少し考えて、消しゴムを掴むと自分の"将来の夢"の欄を消した。
そして鉛筆を握り締めてその上から新たに書き込んだ。
"塔子の翻訳した絵本を一番に読む"
書き終わって顔をあげると、とーこが覗き込んでいて、みるみるうちに頬を赤くした。
「俺の将来の夢、だから」
笑ってそう言うと、とーこは「なにそれ!」と言いながら、でも転がした鉛筆を掴むと先程消した跡をなぞるように、何か書き込んだ。
俺は頬杖ついて微笑んだ。
"翻訳家"
そしてその隣に
"直人に一番に読んでもらう"
と書き足して。
「・・・約束ね?」
とーこは書きながら言った。
「約束な」
俺は頷いて言った。
いろんな約束を・・・俺たちは無邪気に増やしてた。
「・・・・・・」
目を開けてすぐ、俺は片手をついて起き上がった。
ぱたんと腿の上に何かが落ちる。
帰宅して、寝てしまったらしい。
ソファーから起き上がって窓の外を見る。
さっきまで、日は傾いててもまだ夕方と呼ぶには早い気がしたのに、今はさすがに窓の外は淡い青に包まれてきてる。
腿の上に落ちてきた・・・文集。
俺はそれを持ち上げて見た。
これを読んでた所為か。
あんな夢見たの・・・。
しばらく視線を手元の文集に落とした。
そのまま動けなくなることを恐れて、俺は無理矢理文集から視線を引き剥がした。
起き上がりテーブルの上に文集を置き、替わりに携帯を手にした。
8月5日 19:13
「――・・・・・けっこー寝ちゃったな・・・」
表示されてる時間に思わず呟く。
「メシ・・・」
ぼんやりする頭をなんとか励まして、キッチンへ視線を移すと、ばあちゃんがちょこちょこと動いてる。
あっついってのに、鍋の蓋がことこと音をたてて水蒸気を昇らせていた。
夢の中で懐かしく感じたのは、ばあちゃんの料理の匂いがしてたからか。
夢、というより記憶されているシーンを追体験する感じだった。
匂いまでリアルに感じて、とーこの声が耳に残る。
それはとても幸せで、とても残酷なこと。
拓に小学校のミニバスの手伝いを頼まれてから、俺はほぼ毎日練習に参加してた。
午後から3時間程度、基礎練習中心の内容で、一緒になってボールを追いかけるのは楽しかった。
『気分転換になるだろ?』
シンに言われたように、最初はそれが大半の目的を占めていたのに、今では純粋に、ミニバスを楽しむ小学生に感化されて、一緒になってボールを追いかけていた。
フォームやフェイントの仕方なんかを教えているときに向けられる視線は、とてもくすぐったいものがあってまだ慣れないけど、"上手になりたい""シュートを決めたい""ドリブルして早く走りたい"というとてもシンプルな想いで、吸収しようとする前向きなパワーの中に居るのがとても心地よかった。
何度も懐かしい道を行き来する中で、鮮明に蘇る記憶に揺さぶられ小さなボクたちが現れては消えた。
それは真夏の太陽が見せる逃げ水のように、掴めそうなほど近くに感じても本当に辿り付ける事はなかった。
時間が経つにつれ、募る想いがあるんだと知った。
もう、自分ではダメなんだと思いながら諦めきれない気持ち。
その絶望的な感覚の中ですら、ふと宿る柔らかな記憶の中の姿に、また焦がれる。
そこから逃れるように駆け出す。
・・・だけど。
眠りにつく瞬間に想うのは、やっぱりとーこのことだった。
俺は揺れるガムランボールを見つめた。
何度も外そうとしてストラップに手をかけた。
もう、とーこに返すべきなんじゃないかって思ってた。
震える指や、とーこはこれをもう捨てたんだ!なんて自分に言い訳して、結局まだ外せないままでいた。
氷の壁はもう俺がよじ登っていけるような高さではなくなっていた。
違う。
とーこを凍らせていた氷はすべて融け、氷の壁は俺だけを取り囲んでいる。
とーこの氷を融かしたのはあいつだ。
そうわかっているのに、それでもまだ、俺はとーこの瞳に宿っていた揺れる想いを諦めきれずに居る。
どこかで微かに期待してる。
――とーこの手は、まだボクに繋がっている。
掌を見つめ、自嘲する。
先延ばしにしてるだけ。
さよならはすぐそこに迫っている。
得体の知れない確信。
「・・・っ」
出口は一つしかないのに、俺は違う出口を探して逆戻りする。
「さよなら」というエンディングから逃れるために。
時間が戻せるわけじゃない、魔法が使えるわけでもない。
選択肢は少ない。
俺には向けられる事のない、とーこの笑顔が見られる「さよなら」
とーこの中に、失くせずにある感情に甘えて、笑顔を取り戻せない「これから」
いつの間に、選択肢がこんなに少なくなってしまったんだろう。
本当はもう、この選択肢すら残されていないのかもしれない。
胸が痛い。
出口のない想い。わかっていても、その出口の前で抗う。
好きだから、大好きだから。
こんな想いを・・・とーこはずっとしてきたんだ・・・。
「ばあちゃん、風呂入ったら?」
煮物の残り物をタッパーに移しながら声をかける。
テーブルの上の携帯が短く電子音を響かせる。
洗剤をつけようとしてたスポンジから手を放し、携帯を持ち上げて開いた。
有菜だった。
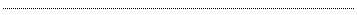
明日、流れ星、楽しみにしてるね。
そして、明日・・・とーこちゃんに話します。
今まで付き合ってくれてありがとう。
これからも友達でいてください。
有菜
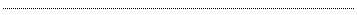
「・・・明日」
有菜に返信しようとボタンを押そうとした。
その時、今度は家の電話が鳴り出した。
「え?」
親機の液晶ディスプレイには・・・とーこの家電の番号が表示される。
伸ばしかけた手がぴたりと止まり、息を飲んだ。
もしかしたら、決定的なことを言われるかもしれない・・・
そう思うと受話器を持ち上げることができず、あと数cmというところで指先が彷徨った。手が震える。
――躊躇する。
「出ないの?」
ばあちゃんが不思議そうな顔でこちらを見ている。
「出るよ?」
俺は苦笑して・・・なんとか受話器を掴み耳元まで持ち上げた。
なんとか搾り出した声で「はい」と応えながら。
『あ、直人君?』
「・・・・・・おばさん?」
耳元に響いたのは、とーこのお母さん・・・おばさんの声。
俺は力が抜けるような気がして、壁に寄りかかりながら窓の向こうに見えるとーこの家の明かりを見つめた。
どこかで、凄くほっとする自分を感じながら。
『こんばんは。あのね、とーこお願いできるかしら?』
「え?」
『?』
「・・・あの、とーこって?」
俺が首を傾げると、受話器の向こうでも『あら?』と不思議そうな声あがる。
『とーこ、直人君のところに行くって・・・そうねえ・・・もう1時間くらい前に家出たのよ?』
行ってない?
おばさんの言葉に、俺は時計を見つめる。
20時28分・・・1時間前?
俺は「いいえ」と答えて窓の外に再び視線を戻す。
「・・・聞き間違いじゃないですか?俺のとこって・・・?」
『直人君家を指差して言ったんだけど・・・あら、じゃあどこ行ったのかしら・・・』
流石に、おばさんの声が心配そうにくぐもる。
『直人君のところだとばっかり思ってたから・・・』
俺は携帯のメール画面を終了させ「一回切ってください。携帯で掛け直しますから」と告げる。
おばさんの返事を待たず、受話器を元に戻し「どうしたの?」と心配そうな顔のばあちゃんに「ちょっと出てくるな」と笑顔を作って言った。
携帯を握り締め、慌てて靴を履く。
・・・凄くイヤな感じがした。
胸がざわつく。
携帯に、諳んじられるとーこの家の番号を打ち込み通話ボタンを押す。
1コールで出たおばさんに「直人です。これから探してみます」と告げた。
やっぱり携帯便利よねえ、なんて呟くおばさんの声は、何故かすでに安心しきった声に変わっていた。
『悪いわね、直人君』
「・・・いえ・・・多分、星見てるんだと思うから・・・」
おばさんと話しながら、俺は野原に向かう。
そこしか考えられなかったから。
もう、ペルセウスのショーは始まっている。
歩きながら、心臓が痛み出すのを感じてた。
この道が、どのゴールに繋がっているのか・・・まだわからなかった。
――27、星空が落とす涙 −1−
2008,3,9up