吉夏社(kikkasha)
![]()
新聞や雑誌などに掲載されたものを抜粋でご紹介しています。評者の方々にお礼申し上げます。
| ┃地下に潺潺たる水の音を聞け┃須山静夫┃ |
|
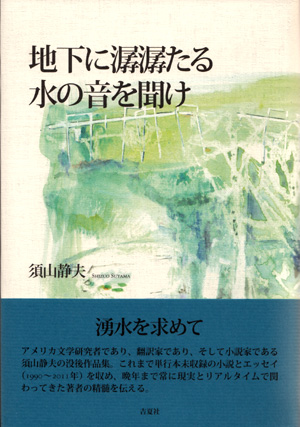 |
『図書新聞』2014年3月8日号(書評)
《どのエッセイからも、どのページからも 須山静夫氏を感じとることができる》 ■■〔本書収録の一篇「『砂の女』の砂」について〕安部公房の代表作、『砂の女』。砂丘の穴の底に住む女に捕えられた男の物語。この小説において「砂」が果たす役割の大きさを疑う者は居ないだろう。だが、この小説の中に何度「砂」という文字が登場するか、数え上げたことのある人はこの世に何人くらい居るだろうか? (中略) この論考の最後の節で、須山氏は突如、視点を池袋のサンシャインビルの展望台に移動させるのである。その刹那、サンシャインビルは砂の棒グラフと化し、眼下に広がる東京は砂漠と化す。そして氏は、自身をも含めたこの世の無数の人間が、既に全身が砂に同化して崩れ去っていることも知らず、ありもしない「未来」に空しい希望をつなぎながら、足掻くように意味のない生を生きていることに気付き、戦慄するのだ。氏はこの時、『砂の女』という小説を読んでいるのではなく、ましてや分析しているのでもなく、この小説の主人公の男と共に砂に埋もれている。これこそが、この生々しい体験こそが、須山氏の小説の「読み方」なのである。 (中略) どのエッセイからも、どのページからも、氏のユニークな思考の働きを、深く沈む思いを、氏のそこはかとないユーモアを、氏の意外にどぎつい諧謔を、そして氏の静かな優しさを、感じとることができる。(後略)■■ 【尾崎俊介氏評】 |
| ┃クレバスに心せよ!┃須山静夫┃ |
|
 |
『図書新聞』2012年10月6日号(書評)
《「翻訳の鬼」の遺著へ捧げるオマージュ》 ■■……アメリカ南部の作家フォークナーやオコナーについてものを書くようになった私は、須山氏がこれらの作家の翻訳者であることを知るようになり、また生半可な翻訳者ではないという、つまり「伝説」の一端に、氏自身の書かれたものを通じて、また氏にまつわる同業者や編集者の噂という形で徐々に触れることともなった。月日は流れ、とうとうその謦咳に接することもないまま、「伝説」の人は逝ってしまった。だから、生きていたその人の証言をもう一度確かめたい、せめてものオマージュを今捧げたいと願い、この遺著の書評をお引き受けすることにした。 ……〔聖書「死海写本」を扱った章について〕これは経文だ。般若心経の一言一句がそれぞれ何を指すのか、気にしながら唱えるものはおるまい(ここでも須山氏だけはきっと例外であろうが)。そこにあるのは、そこにあるだけで尊い、ひたすら道を究め続けようとした人の足跡でこそあって、こうした求道精神とは無縁の衆生は、何の衒いもなく淡々と綴られた悟りへの道程たるこの一書をおし抱き、その文句を口の中に唱えさえすればよい――そういう気持ちに私はなった。 ……写本を行ったのは誰なのかわからないのだが、須山氏は「[この写本の宗教学的価値のみを云々するようなものは]死海写本の筆記者の敬虔な熱意と、精神の持続的な集中力に感動しないのだろうか」と言う。私は同じことを須山氏の仕事に感じてよい、いや、感じなければならないと思ったのだ。■■ 【後藤和彦氏評】 |
|
『出版ニュース』2012年7月中旬号(紹介)
■■本書は、数々のアメリカ文学作品の翻訳を行ってきた著者が、自身のおかした誤訳や、他の日米の研究者たちの誤読、誤訳を記したものである。作品の全体のイメージを木像に置き換えれば、ウィリアム・フォークナーの『八月の光』は新薬師寺の怒髪天を衝く伐折羅大将像で一閃のもとに悪鬼どもを撃ち殺さんばかりの眼球そのものの勢いと、口の奥から噴き出す「阿」という激しい声を、翻訳者は観衆の前に、読者の前に掘り出して見せねばならず、鑿を握る手もとを狂わせて、舌の先を僅かにでも削りすぎるなどはもってのほかだと説く。『白鯨』の訳書では5ケ所の訳について10名の翻訳者の誤訳ゼロの者がいない正誤一覧表まで作り、出版年が新しくなるにつれても誤訳が少なくなる傾向がないといい、翻訳とは「常に仕上げの冠石を後世に遺す」ものだと述べている。■■ |
|
|
『毎日新聞』2012年5月6日(書評)
《きびしく穏やかに、文字とことば見つめる》 ■■……本書全体から知ることは、作品を論じる人たちが原典の文字の書き写しで、おびただしい数のあやまりをおかしている点だ。そのクレバス(裂け目)からは、誤読が拡大。自戒をこめながら淡々と照合をつづける著者の姿は、作品を正しく読みとり、うけつぐ人のもの。きびしさだけではない。ひろいところで思い描くことのできる人の穏やかさがある。 最後の「『死海写本 イザヤ書』に分け入って」は、死海のクムラン洞窟で発見された「死海写本」(紀元前二世紀)に、ほとんど筆写のあやまりがないことを検証。「文字を書くことに対する姿勢が根本的に厳粛を極めていたのではないか」。クムランの筆記者の「熱意、集中力」への感動を次のように記す。 「かりに彼が窓の外に目をやったとしても、見えるのは、岩と砂利と砂だけだ。目を楽しませてくれるものは一つもない。空は曇っているかもしれない。晴れているかもしれない。その空も広々とした空ではない。周囲の岩壁で狭く限られている。こういうところに彼はいた。だから彼はこういう仕事をすることができた。」 著者もまた、このような「仕事」をつづけたために、こんなすてきな本を書くことができたのだと思う。■■ 【荒川洋治氏評】 |
|
| ┃アイザック・B・シンガー研究┃大崎ふみ子┃ |
|
 |
『毎日新聞』2010年3月14日(書評)
《作品から生じる全光景に目をとめて》 ■■……一冊の本を読む。あるいは数冊の読書から感想や印象を引き出すのが、通常の読書。研究の読書は、そうした一般社会の原則から離れたものである。邦訳があるかどうかといった枠にもとらわれず作品を読み、できるだけ広いところに立って価値を見定め、遠回りではあるが、そのことによって「社会」とのつながりを果たそうとするものである。 だから「ここがいい」「ここがおもしろい」というような、個人的なことばや感想が記されることはない。「愛する者、そしてすべてのはかない存在が、時を超えた存在者の胸に抱きとめられているという、悲しみをともなってはいるが、深く心にしみ渡る大きな慰めである」。本書のことばとは、こういうものである。要所においても、色づかいは地味である。だが全体を読んでいくと、文学についてとどめおくべきことがらが、よりたしかなものになっていることに気づく。すぐれた作品を前に人はどうしてきたか。そのあと、どんなことが起きるのか。作品という世界から生まれる、すべての光景に目をとめる。できるかぎり、こまやかに見る。それはいまや見失われた、読書の道筋でもあるのだ。■■ 【荒川洋治氏評】 |
|
『図書新聞』2010年4月24日号(書評)
《「時の消滅を阻む」作品世界の魅力 ――シンガーの世界を読み解くまたとない手引き》 ■■……抵抗と謙遜、信仰と懐疑、絶望と希望は私達の精神に同時に住まうことができる――。シンガーはそう述べて、だからこそ人間には自由になる選択が存在するのだと述べたのだった。 『悔悟者』のなかには、「ヒトラーが権力を得たときにイェシヴァ〔ユダヤ教の宗教専門学校〕がなんの役に立ったか?」ということばがある。二〇世紀の悪と信仰の問題を考えるとき、永遠の箴言のように響き続けることばである。ホロコーストは、シンガーが生まれたポーランドをはじめ東欧の各地にあったユダヤ共同体を根こそぎ破壊した。この共同体では、シンガーの父がそうだったように、現世ではなく、現世を越えた神の世がまことの世界であるとする世界観が古くから保たれてきた。だが、ホロコーストは現世の暴力でもって、この世界観をユダヤ共同体もろとも破壊した。 人間に対する暴力と迫害が頂点に達したホロコーストを前に、神への抗議はとどまるところを知らない。現世を生きる人間は、なぜこれほど苦しまなければならないのか。シンガーは小説世界の随所でそう問いながら、苦しむ者たちへの共感と愛情をにじませる。そしてここに、冒頭にかかげた「私の書くものは実際、すべて回想録だ」ということばが生きている。彼は神に抗議しながらも、失われた世界の記憶を作品に湛えた。 シンガーは一九七八年に発表した『ショーシャ』で、「文学の目的は時の消滅を阻むこと」だと書いた。このことばもまた、シンガーの小説世界が貫くモチーフを示している。一九八五年発表の「なぜヘイシェリクは生まれたのか」(『タイベレと彼女の悪魔』所収)では、「宇宙のどこかに、人間のあらゆる苦しみや自己犠牲の行為が保存されている記録保管所があるに違いない」と書いた。大崎氏は、この記録保管所にある物語を一つ一つ語ることによって、シンガーは「時の消滅を阻む」という目的を見事に果たしていると述べる。……■■ 【米田綱路氏評】 |
|
|
『出版ニュース』2010年4月中旬号(紹介)
■■……本書は、シンガーの独特な作品世界を考察する。永遠の世界への憧憬と創造主に対する抗議、神の世と人の世の現実、聖者と死者、ユダヤ的価値観と非ユダヤ的価値観などを対比させ、聖性とは無縁に思える混乱した現実世界と、そこに生きる人々を描くことを通じて、物語の中に彼方の世界を織り込んでゆく。ここでは、最初の長編小説『ゴライの悪魔』、ポーランドのユダヤ人社会を描いた『荘園』『モスカット一族』、アメリカに渡ったユダヤ人たちの物語『ハドソン川に映る影』などの作品に通底する今は亡きユダヤ人共同体の精神風土を浮き彫りにしてみせる。■■ |
|
| ┃タイベレと彼女の悪魔┃アイザック・B・シンガー┃ |
|
 |
『産経新聞』2007年12月3日(書評) 《イディッシュ語で描いた真実》 ■■……既刊のシンガー短篇集(『短い金曜日』『羽根の冠』『情熱』『まぼろし』)から10作を選んで1冊にした独自の編集で、それだけでも出色に恥じない企画である。ここには、人間の孤独、心に住む魔性、生と死の交錯、無償の価値、といったシンガー終生のテーマがほとんど無造作ともいえる装いで提示されているのだが、その無造作の中に編訳者の慧眼が生きているところは見逃せない。 闇があっての光という、価値の逆転、ないしは相対化もシンガーが好んであつかった命題である。この紙幅で個々の作品にまでは触れられないが、表題作「タイベレと彼女の悪魔」から巻末「天国への蓄え」に至る10編を通読すると、シンガーが虚構に真実を求め、またある時は、真実が虚構を生む人間のふるまいに微苦笑を浮かべている様子が知れる。 訳者は本書を編むにあたって「シンガーの全体像がうかがえるものとなるよう配慮した」という。その意図は十分に果たされた。近頃、貴重な一書である。■■ 【池央耿氏評】 |
|
『週刊朝日』2007年12月14日号(書評)
《物語の背後に日常を超える「ひろがり」が見える》 ■■人間はなぜ物語を求めて、書いたり読んだり、語ったりしつづけてきたのだろう。これはきっと人の心や言語の本質と結びつく問題なのだ。日常的な場面をこまかく描写すれば小説になる、というわけではない。遠いもの、目の前にないもの、けれど心の痛点に触れてくる、リアルな刺を持つもの。物語の背後に日常を超える「ひろがり」が見えるとき、それをただ「幻想的」という表現で片づけることはできない。…… シンガーは確かに、ユダヤを描いた。流浪と迫害の歴史を負い、ユダヤ教とその習俗を受け継ぎ伝える民族に属する作歌として。とはいえ、その作品は、閉じられたものではない。むしろ開かれている。こんなにも特殊を描いたように見えて、なぜ深くから開かれているのだろうか。普遍的、という言葉でまとめる手前に留まり、物語そのものを味わいたい。個人の枠を超え、宿命的な流れに繋がるその小説には、重さと明るさがある。いつ、どこで読んでも。■■ 【蜂飼耳氏評】 |
|
|
「二〇〇七年読書アンケート」『みすず』2008年1・2月合併号、みすず書房(紹介)
(※「二〇〇七年中にお読みになった書物のうち、とくに興味を感じられたものを挙げてください」というアンケートに対して) ■■……アイザック・B・シンガーは、故国の破壊されたシュテットル(ユダヤ人村)のフォークロア(の記憶)を自身の創作の宝庫として、ユダヤ人コミュニティの特殊な背景から、名もなき人々の一回限りの生の(それゆえ普遍的な)喜怒哀楽をあぶりだす。表題作をはじめ、切なく哀しい短篇十篇が、シンガーの物語世界への深い共感と敬意の念をもつ研究者によって、見事な日本語に訳されている。■■ 【川端康雄氏評】 |
|
|
『みるとす』2008年2月号(書評)
■■短篇10篇よりなる本書は特異な作品であるが、なにが特異かといえばそれはイディッシュ語による、失われた東欧ユダヤ世界に由来する物語であるからだ。離散のユダヤ社会とそこに生きた人々の生活を彷彿とさせてくれる。もっとも最初は馴染みにくいかもしれないが、親切な用語解説があるのでじっくりと噛みしめれば、思わず不思議な世界に引き入れられて、読書の醍醐味を満喫することだろう。 ……悪魔ですら住めない人間の世界、生と死の交錯する世界、東欧ユダヤの価値観、無償の友情、人間の自己犠牲や苦しみを保存する「天の記録保存所」など、重たいテーマを底流にユダヤ・ユーモアで明るく包むような、シンガーの語りは、日本人にも人生を再考させてくれるだろう■■ |
|
| ┃愛されえぬ者たち┃アルノシュト・ルスティク┃ |
|
 |
『図書新聞』2007年6月9日号(書評) 《二〇世紀が二〇世紀たる根本的なものを内包した物語 ――「歴史における人間」の自由とその省察》 ■■裸になることは、特別な意味を持っていた。それは彼女にとって「始まりと終わり、瞬間と永遠、高慢と謙遜とを同時に意味する」ものだった。自信と誘惑と――それは彼女のいう「ほんの少ししか取り戻せないのに、いやというほどむしり取られてしまう時代」に、それでもなお、ほんの少しなりとも取り戻せるものだったのかも知れない。人間は自由である、しかしその自由は「歴史の必然性」に拘束された者の自由である。そうした二〇世紀の苛酷な歴史経験は、この物語にえがかれたペルラ・Sの心情、そして彼女を取り巻く状況に、「死は人間を生きているときより偉大にする」ということばの意味を響かせる。 この人は実際にどういう人であって、どういう人でなかったかと、万人に対して最終的に審判を下せるのは死だけなのだ。そのときはじめて、生について知ることができる――そう本書は物語る。それは二〇世紀が二〇世紀たる根本的なものを内包した、ルスティクの歴史経験の真実だった。彼は現代に、その経験の意味を問いかける。■■ 【米田綱路氏評】 |
| ┃カフカ=シンポジウム┃クラウス・ヴァーゲンバッハ他┃ |
|
 |
『出版ニュース』2005年8月上旬号(紹介) ■■新改訂版カフカ全集の編集者であり、生涯をカフカ研究に捧げたマルコム・パスリーをはじめ5人の研究者によるカフカの網羅的研究。 カフカの作品とその背景については今なお、数多くの謎に包まれていると言われるが、ここではカフカの実際の草稿や創作ノート全般にわたって詳細な調査・研究を行ない、作品の成立時期、作品中に秘められた意図、現実世界との関連、同時代の批評家による評価など、数多くの疑問が解明されてゆく。例えば『城』の場所について、『十一人の息子』がそれぞれどの作品を指すか、またカフカの2番目の婚約者についての謎など、知られざるカフカ像とその作品世界が見えてくる。■■ |
|
┃ルブリンの魔術師┃アイザック・B・シンガー┃
|
|
|
『図書新聞』2000年5月13日号(書評) 《破滅の深淵は今にも彼を飲み込もうとする…》 ■■この小説の主人公ヤシャ・マズルは、手品や曲芸をなりわいにしている魔術師であり、ルブリンの町では謙譲の妻エステルとかなり裕福な生活を営み、ピアスク町には、夫に蒸発された女で派手好きのゼフテルや、曲芸助手として雇っている若い娘マグダがいて、ともに情欲行為の相手であり、主な興行地ワルシャワには教授未亡人エミリアと十四歳の娘ハリナがおり、その両方を熱烈に恋している多情多感の四十代男である。……だが、この一種の女性遍歴譚は、ヤシャの艶福な生活がいつまでも続く形では進行しない。 ……無頼無惨の精力を発散させつつ放縦の生活に血道をあげたヤシャが、階上からの失墜という破局に遭遇し、翻然と侮悟して、禁欲の聖者へと自己を修復する過程を形象化し、そこにシンガーは一つの完結した小説世界を創造した。■■ 【邦高忠二氏評】 |
|
| 『朝日新聞』2000年3月12日(書評) 《愛は多忙で四苦八苦 男とはかくも悲しい》 ■■十九世紀末、ルブリンのおおもの魔術師ヤシャの、愛と波乱と反省の物語である。 ……シンガーの文章は、平明で文学的ではないので退屈気味。それだけにぼくはいつも、はじめて小説というものを知ったような、まあたらしい気持ちになれる。 ……ひとりひとりの言葉に、心の中にうそがない。真実だけがとうとうと流れていく文章なのだ。人はどの場においても、その人であること以上にその人ではない。そういう、人間の物語を書く。愛する。記憶する。それがいまも読む人を魅了する、作者シンガーの魔術である。■■ 【荒川洋治氏評】 |
|
| 『みるとす』2000年4月号(書評) ■■三十代後半のヤシャは、ユダヤ教の掟を愚直に守る共同体から離れ、西ヨーロッパの近代社会にあこがれる。彼の心は葛藤に苦しんでいた。旅先での自堕落な生活のむなしさ、危険な宙返りをする生活があと何年続けられるのか? ポーランド貴族の未亡人エミリアと結婚するために、カトリックに改宗すべきか? ついにヤシャは、彼女を自分につなぎとめておくために、金庫から金を盗みだそうとする。 ……著者のシンガーはワルシャワのラビの子として生まれ、後にアメリカに移住。1978年にはノーベル文学賞を受賞しており、本書は著者の傑作の一つといわれる。■■ |
|
| 『読書人』2000年12月15日号(紹介) ■■「おはなし」的な小説はぼくにはいちばん遠いものと思っていたが、読み方を心得ることで新しい世界に出会えることをおしえられた。こういう場面ではこう書くしかないという文章が続く。きれいな小説だ。■■ 【荒川洋治氏評】 |
|
|
┃ショーシャ┃アイザック・B・シンガー┃
|
|
 |
「書評執筆メンバー32人への質問」『日曜の朝は今週の本棚』毎日新聞・書評欄PR誌(紹介) (※「今まで『今週の本棚』に書いた中で、思い出に残る書評は何ですか?」という質問に対して) ■■2002年11月3日付『ショーシャ』 理由一、はかなく消えゆくイディッシュ語で書かれた最後のはかない愛の物語。この傑作小説は、また、おそらく真の意味で、人類が手で書いた最後の物語・書物となるだろう。そのような本にめぐりあえた幸運に感謝して。……■■ 【辻原登氏評】 |
| 「二〇〇三年読書アンケート」『みすず』2004年1・2月合併号、みすず書房(紹介) (※「2003年中にお読みになった書物のうち、とくに興味を感じられたものを挙げてください」というアンケートに対して) ■■「人間のあらゆる苦しみや自己犠牲の行為が保存されている記録保管所」であるという「世界の本」の話が語られる。このシンガーの小説の語り口と世界性についてはよく考えてみたい。■■ 【宇野邦一氏評】 |
|
| 「翻訳書アンケート 私のベスト10」『eとらんす』2003年4月号、バベルプレス(紹介) ■■両次大戦期間期のユダヤ人たち、その命、生活、愛を染み入るように描く。死者の記憶が生者をつなぐ。最後に呟かれる「苦しみに答えなどない」、それは20世紀の真実を開く呪文であろうか。■■ 【米田綱路氏評】 |
|
| 共同通信社 配信記事 2002年7月下旬〜8月中旬(書評) 《長らく読みたいと思っていた》 ■■物語は、二本の糸をより合わせるようにして語られている。一つは、このクロホマルナ通りの住人たちのこと。変人、奇人、奇妙な情熱に憑かれた者たち。人々の暮らしの中にあって、正当派ユダヤ教の教義が目を光らせ、ひそかに運命観と、この世の見方をささやきかけてくる。おりしも隣国ドイツの雲行きがただならない。ヒトラーが政権を掌握、公然とユダヤ人弾圧に乗り出した。 ……これを横糸とすると、少女ショーシャが縦糸に当たる。主人公の幼友達であって、「九歳だったが、六歳のような話しぶり」。目が青く、鼻筋が通り、首が長かった。共に成長し、たえずかたわらで話を聞いてくれる。「君がいる限り、僕の人生にもまだ何らかの意味がある」。精密な描写の一方で、何気ないやりとりの中に時空間を超えて宇宙的な広がりを持つ、ユダヤ的な比喩に託されたエピソードが美しい。それは本来、伝えられないものを伝える語りなのだ。■■ 【池内紀氏評】 |
|
| 『産経新聞』2002年8月10日(書評) 《ノーベル賞作家 円熟の傑作》 ■■一九三〇年代の後半、ヒトラーのナチスドイツとスターリンのソ連に挟まれ、いつ侵攻されてもおかしくない絶望的な状況にあったポーランド。そんな中、信仰にもイデオロギーにも満たされず、女たちの愛に翻弄されるようにして生きていたユダヤ人青年が、ワルシャワの貧民街クロホマルナ通りで「奇跡」に出会う。知能の発達がおくれ身体の発育も止まってしまった幼なじみの女の子ショーシャが、二十年前とほとんど同じ姿で同じ場所に住んでいたのだ。腐った果物や煙突の煙の臭いとともに立ちのぼる少年時代の思い出。その昔、自作の「お話」をすると懸命に耳を傾けてくれたショーシャは、駆け出しの作家であるこの青年にとって、淡い初恋の相手でもあり、創作活動の原点でもあった。…… 〔主人公〕アーロンを取りまく女たちがそれぞれに魅力的だ。彼の才能を認め、なんとかアメリカに逃してやろうとする女優ベティの知性と激情、憧れていたソ連共産主義の現実を知って失望し自殺をはかるドラの肉体の魔性、活力にあふれたポーランド娘テクラの純朴さ、自分の居場所を見出せずに苦しむ人妻シーリアの官能。でもアーロンは、そのいずれよりも、あどけないショーシャの無垢の魂を深く愛した。その中に「自分自身が見え」、失われゆくユダヤ人社会と子供時代の残像が永遠にとどめられていたからにちがいない。■■ 【沼野恭子氏評】 |
|
|
『毎日新聞』2002年11月3日(書評)
《彼女はどこへ‥‥震えるようなラスト》 ■■ショーシャは、ワルシヤワの、ゲットーと呼ばれてもよいような貧民街クロホマルナ通りに生まれた少女。知恵遅れで、発育不良で、かつ美しい。幼なじみの〈私〉は少年のとき、すでに彼女への永遠の愛を誓っている。…… しかし、〈私〉はやがてゲットーを出てゆき、物書きになる。作家クラブに出入りし、女たちとの快楽にふける。アメリカから来たイディッシュ語劇の女優とねんごろになると、女優が彼の育ったゲットーが見たいという。〈私〉は二十年ぶりにクロホマルナ通りにもどってくる。ショーシャがいた。ほとんど二十年前と変わらない姿で。…… ここから〈私〉とショーシャのなんとも胸を抉られるような愛のドラマがはじまる。もうまもなくヒットラーがやってくる。〈私〉は、ショーシャをクロホマルナ通りから引き出したら、水の外に出した魚のようにたちまち死んでしまうことを知っている。だからワルシャワにとどまる。…… ラストが震えるほどすばらしい。どんな小説にもラストはあるが、これをラスト・ベストテンに数えよう。『審判』のラストや『蓼食う虫』、『存在の耐えられない軽さ』のラスト、等々の中に。■■ 【辻原登氏評】 |
|
| 「2002年『この3冊』」『毎日新聞』2002年12月22日(紹介) ■■『ショーシャ』は、東欧流浪ユダヤ人の言語、イディッシュ語で書かれた最高の恋愛小説。イディッシュ語は滅んでも、ショーシャは永遠に生きる。■■ 【辻原登氏評】 |
|
| 「半歩遅れの読書術」『日本経済新聞』2006年5月28日(紹介) 《傑作の条件 震えるようなラストこそ》 ■■……小説は、僕たちの人生の似姿を凝縮して提供する。つまり小説の第一行は誕生であり、最後の一行は死の断崖絶壁なのである。誕生は偶然であり、死は必然である。と考えれば、僕がラスト重視主義なのが分かってもらえる。 ラストに震える。これが僕の傑作の条件だ。 ずっと僕のラスト・ベスト3は、『審判』と『蓼食う虫』と『存在の耐えられない軽さ』だった。最近、これに震えるほどすばらしいラストの作品が加わった。アイザック・B・シンガーの『ショーシャ』である。 ……ずっとこの小説にはまっている。何という美しい物語、そして何という震えるようなラストだろう?……■■ 【辻原登氏評】 |
|
| 『朝日新聞』2002年10月20日(紹介) ■■ナチスによるホロコースト直前のポーランド。ユダヤ人で作家の主人公は幼なじみのショーシャに再会し、まるで幼女のままの彼女との結婚生活が始まる。シンガーの小説ではいつも、登場人物がごく自然に真実を語る。ある女優が言う。「いつでも私の最悪の敵は私だったわ」。生きるとは何なのか、深く考えさせられる長編。■■ |
|
| 『出版ニュース』2002年9月中旬号(紹介) ■■作者の分身とも見える主人公アーロンは、幼なじみのショーシャと再会する。ショーシャはなぜか20年前に別れた少女の姿で登場するが、物語はアーロンとショーシャとの対話を軸に進行しながら、消し去られたユダヤ人社会の人間模様が展開する。ここから浮かび上がってくるのが、作者の死者たちへの思いであり記憶である。シンガーの自伝的回想を織り込みながら、〈文学の目的は時の消滅を阻むこと〉という主人公の語りに凝縮された作者の切実な問いかけが伝わってくる。■■ |
|
|
┃悔悟者┃アイザック・B・シンガー┃
|
|
 |
『図書新聞』2004年2月21日号(書評) 《放浪性と孤立性を重ね合わせて》 ■■私がシンガーを知り、数々の作品を読み漁った当時はまだ英訳されたペンギン版しか書店には並んでいなかった。あらかた内容は忘れてしまっているが、ユダヤ人なるがゆえのホロコースト(大虐殺)にさらされる悲惨と絶望に暗澹たる思いに捉われた記憶だけは今もたゆたっている。ユダヤ人の放浪性と孤立性はホロコーストの悪夢をはらんだ象徴でもある。 ……〔主人公〕シャピロはシンガーの分身とも読み取れる。ユダヤ人の放浪性と孤立性に救済を求めるとすればどうした形が望ましいかという一つの答えが『悔悟者』ではないだろうか。■■ 【元秀一氏評】 |
| 『出版ニュース』2004年3月上旬号(紹介) ■■……現代社会におけるユダヤ人の生き方、あり方を描いた意欲作である。……著者は、イスラエル社会のマイノリティの存在を浮き彫りにすることで。「本来あるべきユダヤ人」とは何かを現代社会批判の文脈で問う。■■ |
|
| bk1 書評 《信仰心が空洞なまま「掟」や「慣習」だけが踏襲される現代のユダヤ教への問い》 ■■小説としての構成はシンプルですんなり読み進めていけるものになっているが、特に最初の方に作者のメッセージ性の高い言葉が頻出している。金欲や名誉欲、情欲を満たしていく成功者の立場から、ユダヤ人としての出自を問いかけ、賢者たちとの出会いに納得のいく生き方を探求していく――だから説教臭い内容なのかというと、そうではない。 作家が自分を含めたユダヤ人を諌めていこうとするのではなく、「ユダヤ人」とくくられる人びとのなかにも、実に多様な「ユダヤ」との関わり合い方があるという説明も企図されているようである。■■ 【中村びわ氏評】 |
|
|
|
『みるとす』2004年2月号(紹介) ■■本書は、父祖のユダヤ人が信仰と一体の生活が可能だった時代と違ってすっかり世俗的になった現代において、「ユダヤ人」という生き方を根本的に問う告白体の小説である。真面目なテーマにしては比較的読みやすく、心にずっしりと響くものがある。……この本の「著者あとがき」も味わいがある。■■ |
| 「2004年上半期読書アンケート」『図書新聞』2004年7月31日号(紹介) ■■同じ版元、同じ訳者のシンガーの秀作『ルブリンの魔術師』(2000)より控えめの内容だが、どこにいても行っても世界は同じというこの世界の正しい味わいが伝わり印象は濃い。……■■ 【荒川洋治氏評】 |
|
|
┃教育者アラン┃ジョルジュ・パスカル┃
|
|
 |
『内外教育』(時事通信社)2000年6月2日号(書評) 《豊かで厳正な教育観を読みなおす》 ■■アランはフランスの哲学者で教育者でもある。十九世紀末からニ十世紀にかけて活躍し、他方面にわたるテーマについて論じた。そのテーマは教育はもちろんのこと、宗教、政治、精神分析から科学、文芸などにわたっている。彼は、問題と正面から向き合い、考えることを楽しんだ。現代のような激動の時代の風潮と比べると、アランの考え方はゆったりして、繊細に見える。しかし、それを支えている論理は、驚くべき厚みを持っている。そのために本書は、現代の風潮を批判的に映し出す鏡のような働きをする。教育論として見ると、アランが重視するのは判断力である。その根拠は、約四十年にわたる教職経験に裏打ちされており、彼が生徒とどのように向かい合ったかを想像させ、ほほ笑ましい。■■ 【堀内守氏評】 |
| 『聖教新聞』2000年7月12日(書評) 《精神形成の哲学者を多角的に》 ■■アランにとって真の教育の目的とは、万人に「精神」を形成し、「啓発された市民」を育成することである。だから常に、教育方針が精神形成に適しているかどうかという点で教育を論じる。…教育は自分の本性を生かし、その本性を支配することを教え、それは「野蛮状態から救い出す第一歩」であると語る。「人間らしいところにまで自分を高めない者は、いつまでたっても気分と本能の奴隷」なのだ。彼の求めた、本当の教育はすべて、同時に道徳教育であり、そして培った自由な精神こそ「最高の人間の価値」なのである。アラン理解のための好個の書である。■■ |
|
| 佐藤学編『教育本44』平凡社(論考) 《「自由な意志」を追求する深く確かな思索》 ■■著者ジョルジュ・パスカルは、アランの孫弟子であり、教育者としてのアランの思想の真髄を彼のプロポの中に見い出して、教育に関するアランの思索を哲学的に探究している。もちろん、アランの思索の研究はアラン自身の著作を読むことを前提としているが、パスカルの『教育者アラン』は、アランの教育論をその骨格に即して明快に提示しており、アランの原著を読まなくとも、アランの思索の魅力を堪能しながら教育の見識を高めることができる好著である。 ……パスカルは本書において、アランの含蓄のある思索を中実にかつ生き生きと再現している。アランの随想にちりばめられていた宝石のようなフレーズが、本書ではいくつかの織物の図柄に組み込まれて再提示されている。アランの原著を読むのも大切だが、パスカルとの対話を通してアランの思索の襞に触れるのも、それに劣らず刺激的である。■■ 【佐藤学氏評】 |
|
|
┃シュルレアリスムと聖なるもの┃ジュール・モヌロ┃
|
|
 |
『新文化』2000年11月23日(紹介) ■■第一次大戦後の今世紀初頭、フランスの詩人アンドレ・ブルトンが起こした芸術運動であるシュルレアリスムは、たちまちヨーロッパ全土に広がり、芸術や思想に大きな影響を及ぼした。それは近代物質文明や合理主義に対して人間性の回復をめざす、ルネッサンスにも比肩する運動だった。その研究書のなかでもとくに評価の高いのが本書で、著者はブルトンと親交篤く、社会学者であると同時にシュルレアリスムの活動家としても知られる。日本では26年ぶりの復刊で、研究者待望の書。■■ |
| 『現代詩手帖』2001年4月号〈特集・シュルレアリスムと戦争〉(論考) ■■[本号に収載の、永井敦子氏による論考「ジュール・モヌロの転成」に、本書の内容と著者についてが詳細に論じられています]■■ |
|
|
┃E・T・A・ホフマンの世界┃エーバーハルト・ロータース┃
|
|
 |
『こどもとしょかん』2001年夏号(紹介) ■■ 「くるみわり人形とねずみの王さま」等の作家で、詩人、音楽家、判事等様々な顔をもち、現代文学にも強い影響を与えた後期ドイツ・ロマン派の奇才の評伝。■■ |
| bk1 書評 《高名な美術史家が照らしだす「マルチ」なホフマン》 ■■本書はコンパクトながら、この作家の生涯をたどりながら、あいだに重要な作品についての解説をおりこんで進行してゆく。時代の流れ、風潮と、そのなかを生きてゆく作家ホフマン。そしてその生から生み落とされる作品。その作品のなかに、時代を読み込み、また時代への照射を読む。…もちろんホフマンの作品を知っていればよし、なんとはなしに興味を持っているという人でも、良き入門書になる本である。■■ 【小沼純一氏評】 |
|
|
┃狩猟の哲学┃オルテガ・イ・ガセー┃
|
|
 |
「読み・解く」『朝日新聞』2002年12月7日(関連記事) 《「砂漠の狐狩り」の必然》 ■■隠喩には魔がある。それを教えてくれたのは、機知の罠や網をいくつも隠喩の襞に仕掛けたホセ・オルテガ・イ・ガセットの文章だった。スペイン内戦の闇をくぐったこの老獪な批評家は、名高い「大衆の反逆」よりも、小品の「狩猟論」に今日性がある。 野の一角で猟犬の遠吠えが響く。ぴんと大気が緊張し、追われる獣の恐怖が一直線に突っ走って、森が一つのベクトルに収斂していく……。 この流麗な名文が狩猟家ならざる哲人、しかも血を見るのが何より嫌いなオルテガの手になるとは驚くほかない。戦火を避けたポルトガルのリスボンで、狩猟狂の貴族のために、狩猟を正当化する弁明の文章の執筆を買って出たが、案の定、趣味の内輪ぼめとはほど遠く、西欧社会の全的崩壊、つまりそのまま大戦の隠喩を書いてしまったのだ。 禽獣と違って、本能の壊れた人間は、そのままだと何をなすべきかを知らない。この虚ろなる所与が、無聊という空虚から逃れるために、天職としての狩猟がある。狩猟を「人間の卓越性への自発的な断念」とみる彼の省察は、卓越を過信した無意味な殺戮のひそかな否定だろう。‥‥ ケインズもオルテガも、大恐慌で露頭した、人間の内奥に発する「焦土」を透視していた。僥倖と言うべきは、続いて起きた大戦と冷戦が「外被」となり、この焦土を半世紀余も覆ってくれたことだろう。 それが20世紀の終わりに剥げた。‥‥マンハッタンにぽっかり空いた「グラウンドゼロ」のように、先進諸国のそこかしこで、労苦なき空虚の爆心地が地上に現れたとも思える。インフレが無限の成長という夢想の余熱なら、米国でもその恐怖が指摘されはじめた「デフレ」は、自明を失った空虚の隠喩ではないのか。 だが、不毛の原野に取り残された人間には、皮肉にも猟すべき獣がいない。そこで、人間自身を駆り立てるしかなくなる。砂漠の狐狩りにも似た「サダム・フセイン征伐」を米国が始めるのは、デフレからの遁走という切羽詰まった必然があるからではないか。‥‥■■ 【阿部重夫氏評】 |
『出版ニュース』2001年7月上旬号(紹介) ■■「狩猟スポーツの霊妙なる原理とは、この上もないくらいに原始的な状況、つまり人間がすでにして人間でありながら依然として動物的な生き方の圏内にあった初発的な状況を、人間の可能性として人為的に永続化することなのである」。……自然の隠喩において社会を語っていくオルテガのアプローチは、内戦後のスペインの状況を洞察するのみならず今日の文明が直面する危機をも予見している。■■ |
|
| 『第三文明』2001年9月号(紹介) 《思想家オルテガの残した"生"をめぐる論考集》 ■■名著『大衆の反逆』でその名を残すスペインの思想家、オルテガ・イ・ガセーの本邦初訳二編を含む一書。狩猟者のごとき油断なき感覚と荒々しい生の雄叫び。自滅の危機に瀕した現代文明を救うのは、そうした強く逞しい感性によって蘇る、不屈の生命力にあると説く。■■ |
|
|
┃ラカンと政治的なもの┃ヤニス・スタヴラカキス┃
|
|
 |
『図書新聞』2003年7月12日号(書評) 《「政治」とラカンの関係をめぐる立場は折りあわない》 ■■ラカンの思想が正しく有効に機能するための条件は、ラカンの思想が現実には力を「もたない」ことだ、と考える人は多いだろう。そして、そうした考えは、けっしてラカンを忌避することを意味するわけではないのだ。享楽の不可能性を説いたラカン理論が、現実社会におけるラディカルな民主主義といかに親和的(ホモロガス)であろうと、それらがあくまでお互いに無縁なものにとどまるからこそ、ラカン理論は教条的調和の実践へ回収されることのない根源的異質性を保ちつづけるのではないか。もし著者の立場に立つならば、つまりラカンがそれほど正しいのならば、ラカンの存在を現実社会におけるひとつの穴としてその限界を問い直すことでこそ、われわれが求める民主主義の争異のトポスに立つことができるのではないか。■■ 【赤間啓之氏評】 |
『recoreco』2003年5・6月号「世界秩序を読み解くための10冊」(書評) ■■必要な政治は、人々を安定した超越的権力の下に調和させることではなく、欠如の現実性を開口すること、例えば、投票システムから逸脱する政治運動を試みることによって、単一の調和から自由である可能性を確保することにある。超越的な権力の欠陥を侵略し、多様な差異の政治を生み出すことこそ、根源的な民主主義の戦略に他ならない。主体構成の詐術から主体を解放することが目指されている。■■ 【橋本努氏評】 |
|
『出版ニュース』2003年4月下旬号(紹介) ■■本書は、ラカンと政治的なものの可能性について論じたもので、ここではまず、ラカン理論の出発点としてラカン的主体とは何かを解明し、ラカン的対象の措定を経て、政治的現実性に関するラカン的読解やラカンの構想を分析する。こうした前提条件をふまえた上で、現代の政治理論や実践にとって重要な領域として、ユートピア的政治がもたらす危機や、来るべき民主主義の内実に引きつけ、ラカン理論が政治的「解放」をもたらす触媒の一つであることをアプローチする。■■ |
|
bk1 書評 《ラカン理論が民主政治を刷新する。少壮学者の力作論考》 ■■……少なくともラカン本人は現実の政治に積極的に参加するような人物ではなかったが、彼の精神分析は現実政治の倫理的基盤の再定礎に貢献し得る重要なヒントをもたらすのだということを、本書は教えている。本論にあたる全五章のうち、最初の三章「ラカン的主体」「ラカン的対象」「政治的なものを包囲する」では、ラカンの精神分析理論や概念装置が政治理論や政治分析にどれほど有用であるかが検証される。後半の二章「ユートピアの幻想を越えて」「両義的民主主義と精神分析の倫理」ではより具体的に、ラカン理論が政治的理想主義の腐敗に抗し、新たな政治的触媒として民主主義の窮地を解放する役割を果たすポテンシャルを有していることが論証される。ラクラウやムフによるラディカル・デモクラシーの構想の発展的継承がここでは見られる。ラカン理論は、政治における「すべての壮大な幻想に関するわれわれの考え方を変えようとする闘いの最前線に位置している」わけである。本書は、ジジェク、バトラー、ラクラウによる討論の書『偶発性・ヘゲモニー・普遍性』(青土社、2002年)での錯綜した議論に、一定の論理的道筋を与える効果を有するものと思われる。日本ではスタヴラカキスはほとんどまだ無名に等しいが、本書の力作ぶりは、ラカン読解における新たな基本書とみなされるに充分な仕事であるといっていい。■■ 【小林浩氏評】 |
|
| →全文はここ。 |
|
|
┃ヴードゥー教の世界┃立野淳也┃
|
|
 |
『出版ニュース』2001年11月下旬号(紹介) ■■本書は、ヴードゥー教の起源に始まり、その歴史や信仰観、神の体系、儀礼などをトータルに解説したものだ。ヴードゥー教はこれまで、妖術や邪悪な風習といった差別・偏見に基づくイメージで流布されるなど、正確に認識されてこなかった。……ここでは、植民地社会の過程と、西アフリカの宗教の展開を背景として描きながら、自然と神、儀礼と憑依の本質に迫る。■■ |
| bk1 書評 《アフリカから切り離された黒人奴隷による「世界の修復」の記録》 ■■アフリカ大陸から切り離された黒人たちによる「自己が生きる世界の修復」をめざす執念が、ブードゥー教の来歴には込められていた。本書はジャマイカやキューバ、ブラジル、アメリカ合衆国ニューオリンズなど、他のアメリカ諸国における類似宗教の実態に言及し、一連の「アフロ・アメリカン宗教」の総体にまで視野を広げている。私たちのアメリカ観にも新しい奥行きを与えてくれる一冊だ。■■ 【佐藤哲朗氏評】 |
|
| bk1 書評 《ハイチの民衆信仰の歴史が明かすクレオール文化の真実》 ■■前半部で著者は、ハイチにおけるスペイン人の植民地支配とアフリカ人奴隷の歴史から語り起こし、ハイチ革命前後の社会的背景を解説する。表向きはカトリック信仰を強要されていた奴隷たちは彼らの土着的な習わしを棄てず、カリブ海のその他の地域と同じように、異なる宗教を微妙なバランスで融合させていく。後半部では、海を越えた西アフリカ起源の民間信仰の神話体系と祭儀が説明され、その特異な秘密結社的集団の内実や舞踏・音楽文化が記述される。ヴードゥー教の多様な世界への招待となろう。■■ 【小林浩氏評】 |
|
