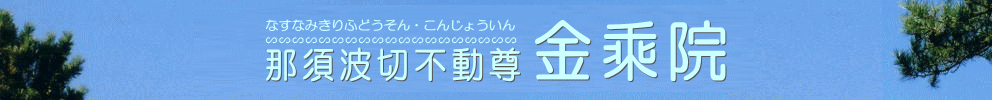
春 夏 秋 冬 |
 芍薬(しゃくやく)-平成19年5月26日撮影- 芍薬(しゃくやく)-平成19年5月26日撮影- |
【花の俳句】 芍薬の花にふれたるかたさかな 高浜虚子 【花言葉】 恥じらい、はにかみ、内気 【花見頃】 5月下旬~6月中旬(2007年) |
【花の俳句】 紫陽花や白よりいでし浅みどり 渡辺水巴 【花言葉】 高慢、移り気、冷淡 【花見頃】 6月中旬~7月上旬(2007年) |
 紫陽花(あじさい)-平成19年6月20日撮影- 紫陽花(あじさい)-平成19年6月20日撮影- |
 蓮(はす)-平成18年7月5日撮影- 蓮(はす)-平成18年7月5日撮影- |
【花の俳句】 一蝶を放ちて蓮華浄土かな 富安風生 【花言葉】 神聖、休養、遠くにいった愛、雄弁 【花見頃】 6月下旬~7月中旬(2007年) |
【花の俳句】 木がくれの海芋の花を仏間より 藤村克明 【花言葉】 すばらしい美、素敵な美しさ 【花見頃】 6月中旬~下旬(2007年) |
 カラー(別名:海芋)-平成19年6月6日撮影- カラー(別名:海芋)-平成19年6月6日撮影- |
 花菖蒲(はなしょうぶ)-平成19年6月6日撮影- 花菖蒲(はなしょうぶ)-平成19年6月6日撮影- |
【花の俳句】 こんこんと水は流れて花菖蒲 臼田亜浪 【花言葉】 優雅、優しい心 【花見頃】 6月中旬~下旬(2007年) |
高野山真言宗 那須波切不動尊 金乗院 栃木県那須塩原市沼野田和571 TEL:0287(65)0076 FAX:0287(65)0238
Copyright (C) 2007 Konjouin All Right Reserved