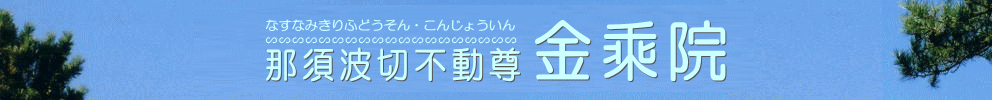

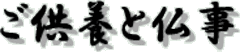
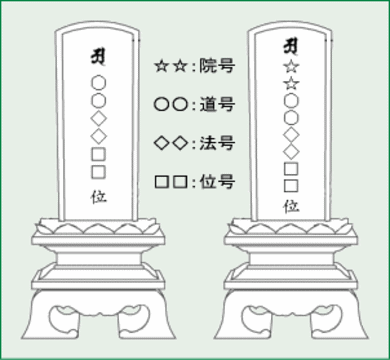 いずれにしても、戒名は仏弟子としての名前であり、故人の場合は、生前の徳を称え、菩提寺の過去帳に記され、後世に受け継がれていきます。
いずれにしても、戒名は仏弟子としての名前であり、故人の場合は、生前の徳を称え、菩提寺の過去帳に記され、後世に受け継がれていきます。戒名の構成は、通常、右図のように上から道号、法号、位号という3つの要素から成り立っています。この中で道号は、もともと仏道を修得した者に対する称号でしたが、今日では謚(おくりな)として、生前の功績や人柄を表わす文字を当てたり、雅号や俳号が用いられることもあります。法号は、法名ともいい、実はこれが正式な意味での戒名です。つまり戒を授かって仏弟子になったという証であり、故人の徳が偲ばれる文字を選んで付けられ、俗名の一文字を折り込むこともあります。
この法号に道号を合わせて、4文字を戒名とする考え方もあります。位号は、仏教に帰依した人を表す尊称で、下記のように年齢や性別により、さまざまな表記があります。また院号は、もともと天皇が出家した時に付けられたことに始まりますが、その後、寺院に対して貢献した人に尊称の意味を込めて付けられるようになり、今日では、寺院名に相応しい文字を当てたり故人の徳を称えた文字を当てたりします。最近では院号、道号、法号、位号の文字列全てをまとめて戒名と呼ぶことが多いようです。
真言宗では、戒名(院号、道号、法号、位号)の上に大日如来の種子である梵字の「ア」を記して大日如来の弟子であることを、子供の場合は「カ」の字を記して地蔵菩薩の守護のもとにあることを表し、下に「位」という字を記します。
| ◆位号の種類 | ||
|---|---|---|
| 成人男子 | ◇ | 信士、清信士、禅定門、居士、大居士など |
| 成人女子 | ◇ | 信女、清信女、禅定尼、大姉、清大姉など |
| 15歳未満の男子 | ◇ | 童子、善童子など |
| 15歳未満の女子 | ◇ | 童女、善童女など |
| 就学前の男の子 | ◇ | 孩児、幼児など |
| 就学前の女の子 | ◇ | 孩女、幼女など |
| 男の乳飲み子 | ◇ | 嬰児 |
| 女の乳飲み子 | ◇ | 嬰女 |
| 死産児 | ◇ | 水子 |
中陰の期間については諸説あり、例えば、死者は最初の7日で「三途の川」の畔に到着するといわれます。「三途の川」には橋が架かり、流れの緩やかな浅瀬と流れの速い深みがあって、生前の業によって「善人は橋」「軽罪の者は浅瀬」「重罪の者は深み」を渡るといいます。そして、この日から7日毎に十王による審判が行われるといわれます。十王とは、いわば冥界における裁判官のことで、下表の通り閻魔大王を筆頭にそれぞれが役割を持っています。十王の中で五七日担当の閻魔大王が重視される理由は、前の四王の取り調べ結果と合わせて、死者が六道の何処に生まれ変わるかを決定する力を持っているからです。その後は、さらに六七日担当の変成王が生まれ変わる場所を決定し、七七日担当の泰山王が生まれ変わる条件を決定するとされています。
| 忌日・年回忌 | 十 王 ( 読 み ) | 本 地 仏 | 役 割 |
|---|---|---|---|
| 初七日 | 泰広王(しんこうおう) | 不動明王 | 殺生について取り調べる |
| 二七日 | 初江王(しょこうおう) | 釈迦如来 | 盗みについて取り調べる |
| 三七日 | 宋帝王(そうていおう) | 文殊菩薩 | 邪淫について取り調べる |
| 四七日 | 五官王(ごかんおう) | 普賢菩薩 | うそについて取り調べる |
| 五七日 | 閻羅王(えんらおう)=閻魔大王(えんまだいおう) | 地蔵菩薩 | 六道の行き先を決定する |
| 六七日 | 変成王(へんじょうおう) | 弥勒菩薩 | 生まれ変わる場所を決定する |
| 七七日 | 泰山王(たいざんおう) | 薬師如来 | 生まれ変わる条件を決定する |
| 百カ日 | 平等王(びょうどうおう) | 観世音菩薩 | |
| 一周忌 | 都市王(としおう) | 勢至菩薩 | |
| 三回忌 | 五道転輪王(ごどうてんりんおう) | 阿弥陀如来 |
一方、死者は葬儀で戒名を授かり、引導を渡された時から仏弟子となり、冥界における修行が始まります。そして、その修行を本尊として守って下さるのが下表に示した「十三仏」という仏・菩薩様です。実は十王は本尊が姿を変えてそれぞれの役目を果たしているもので、十王(本地仏)が配当された三回忌以降は、七回忌の阿しゅく如来、十三回忌の大日如来、三十三回忌の虚空蔵菩薩が、本尊として修行を見守ってくださいます。
| ■忌日・年忌と十三仏(ご本尊) | ※青色のご本尊は十三仏に、その後加わった仏様です | ||
|---|---|---|---|
| ◇初七日(しょなのか) | 不動明王(ふどうみょうおう) | ◇七回忌 | 阿しゅく如来(あしゅくにょらい) |
| ◇二七日(ふたなのか) | 釈迦如来(しゃかにょらい) | ◇十三回忌 | 大日如来(だいにちにょらい) |
| ◇三七日(みなぬか) | 文珠菩薩(もんじゅぼさつ) | ◇十七回忌 | 大日如来(だいにちにょらい) |
| ◇四七日(しなぬか) | 普賢菩薩(ふげんぼさつ) | ◇二十三回忌 | 般若菩薩(はんにゃぼさつ) |
| ◇五七日(ごしちにち) | 地蔵菩薩(じぞうぼさつ) | ◇二十五回忌 | 愛染明王(あいぜんみょうおう) |
| ◇六七日(むなぬか) | 弥勒菩薩(みろくぼさつ) | ◇二十七回忌 | 大日如来(だいにちにょらい) |
| ◇七七日(しちしちにち)49日 | 薬師如来(やくしにょらい) | ◇三十三回忌 | 虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ) |
| ◇百カ日(ひゃっかにち) | 観世音菩薩(かんぜおんぼさつ) | ◇三十七回忌 | 金剛薩た(こんごうさった) |
| ◇一周忌(いっしゅうき) | 勢至菩薩(せいしぼさつ) | ◇五十回忌 | 大日如来(だいにちにょらい) |
| ◇三回忌(さんかいき) | 阿弥陀如来(あみだにょらい) | ||
高野山真言宗 那須波切不動尊 金乗院 栃木県那須塩原市沼野田和571 TEL:0287(65)0076 FAX:0287(65)0238
Copyright (C) 2007 Konjouin All Right Reserved
